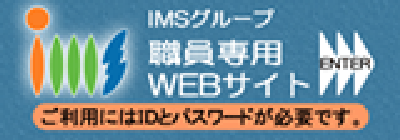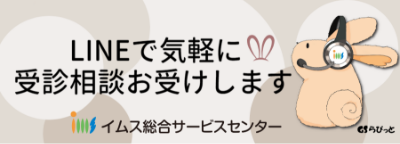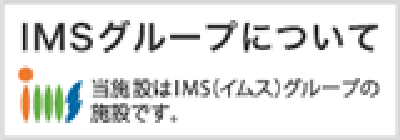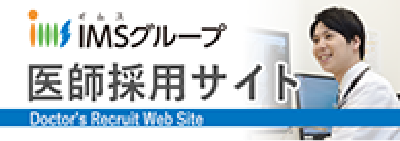リハビリテーションセンター

成果にこだわる
リハビリテーションの実践
- 1回毎の訓練時間を大切にし、常に成果を求め振り返り実施していきます。
- 患者さまや利用者さま、同僚、多職種、自分自身に気を配り、モチベーションが高まる接遇を心がけ実践していきます。
- 従来のリハビリテーションに捉われず、患者及び社会から望まれる技術を身につけていきます。
役割
「リハビリテーション」(Rehabilitation)は、re(再び、戻す)とhabilis(適した、ふさわしい)から成り立っています。機能回復だけではなく、「人間らしく生きる権利の回復」や「自分らしく生きること」が重要で、そのために行われるすべての活動がリハビリテーションです。
理学療法士(PT)は、基本動作能力の向上を目的に運動療法や徒手療法を用いて身体機能の改善や再構築を行います。作業療法士(OT)は、食事や着替え、家事や趣味など生活を送る上で欠かせない活動ができるよう治療、援助、指導を行っています。言語聴覚士(ST) は、コミュニケーションや摂食嚥下(食べる事、飲み込む事)に問題がある方に検査、評価、訓練、指導、助言を行います。
入院当初から退院後の生活を想像し、患者さま、ご家族さまと共にその人らしい生活が送れるよう支援しています。そのためにも1回毎の訓練時間を大切にし、従来のリハビリテーションに捉われず、常に成果を求めた実践を心掛けています。
Message患者さまへメッセージ
当院では患者さま主体のリハビリテーションが提供できるよう心掛けています。そのためお身体のことや生活スタイルをお伺いし、その方の希望や思いに沿った治療を実践しています。
住み慣れた地域でその人らしく生活できるよう、サポートさせて頂きます。
関連ページ
>リハビリテーション科
さまざまの病気により動けない、話せないなどの障害を診断し治療する科です。
>>PT・OT・ST
当センターの各職種採用情報をご案内しております。
ごあいさつ
当院は超急性期から回復期、生活期及び小児から成人、高齢者と幅広いリハビリテーションを展開している総合病院です。患者様や利用者様の人生に責任を持ち、理学療法、作業療法、言語聴覚療法それぞれの専門性を最大限に生かし「結果と成果」にこだわり実践しています。
今後は、訪問リハビリテーションの強化を進め、地域、社会から選ばれ必要とされる新しい事業にも挑戦していきます。

リハビリテーションセンター技士長
福留 大輔
作業療法士
IMSリハビリテーション部門 副統括責任者
東京工科大学 医療保健学部 臨床教授
ADOC共同研究者
福留 大輔
作業療法士
IMSリハビリテーション部門 副統括責任者
東京工科大学 医療保健学部 臨床教授
ADOC共同研究者
スタッフ(令和5年4月現在)
- 理学療法士(PT)
- 82名
- 作業療法士(OT)
- 50名
- 言語聴覚士(ST)
- 24名
- あん摩マッサージ師
- 1名
- リハ助手
- 5名
- 3学会合同呼吸療法認定士 10名
- 心臓リハビリテーション指導士 1名
- 認定理学療法士(循環器1名)
- 作業療法士臨床実習指導施設認定病院生活行為向上マネジメント(MTDLP)実践者 2名

施設基準
- 脳血管等リハビリテーション料(Ⅰ)
- 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
- 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
- 心大血管リハビリテーション科(Ⅰ)
- がんリハビリテーション料
- 訪問リハビリ(医療保険、介護保険)
- 回復期リハビリテーション科 入院料(Ⅰ)
体制
365日体制
(急性期、回復期、障害者病棟の休日リハビリテーションの実施)
(急性期、回復期、障害者病棟の休日リハビリテーションの実施)
基本方針
成果にこだわるリハビリテーションを実施します。
- 1回毎の訓練時間を大切にし、常に成果を求め振り返り実践していきます。
- 患者さまや利用者さま、同僚、多職種、自分自身に気を配り、モチベーションが高まる接遇を心がけ実践していきます。
- 従来のリハビリテーションに捉われず、患者さまから望まれる技術を身につけていきます。
リハビリテーションについて
「リハビリテーション」(Rehabilitation)は、re(再び、戻す)とhabilis(適した、ふさわしい)から成り立っています。
単なる機能回復ではなく、「人間らしく生きる権利の回復」や「自分らしく生きること」が重要で、そのために行われるすべての活動がリハビリテーションです。
疾病や怪我の治療後に以前の状態に可能な限り近づけること、加齢に伴う退行変性や老化の予防・維持等を医師の指示のもと、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)が協働し治療を行います。
単なる機能回復ではなく、「人間らしく生きる権利の回復」や「自分らしく生きること」が重要で、そのために行われるすべての活動がリハビリテーションです。
疾病や怪我の治療後に以前の状態に可能な限り近づけること、加齢に伴う退行変性や老化の予防・維持等を医師の指示のもと、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)が協働し治療を行います。
理学療法
理学療法とは、病気、けが、障害などによって身体機能が低下した状態にある方に対し、座る、立つ、歩く等の基本動作能力の向上を目的に運動療法や徒手療法を用いて身体機能の改善や再構築を行います。また、温熱、電気、超音波などの物理機器を用いた物理療法にて疼痛緩和などを図っていきます。当院においてはインソール(足底板)療法やテーピング療法、装具などを用いた訓練も行っています。
対象者ひとりひとりにおける身体能力や生活環境等を十分に評価し、それぞれの目標に向けて適切なプログラムを作成し、治療に当たっています。
対象者ひとりひとりにおける身体能力や生活環境等を十分に評価し、それぞれの目標に向けて適切なプログラムを作成し、治療に当たっています。



作業療法
作業療法とは、こころとからだを元気にし、自分らしい生活を送るためのリハビリテーションです。
私たちは、食事や着替え、家事や趣味など生活を送る上で欠かせない活動ができるよう治療、援助、指導を行っています。当院は総合病院であるため、入院当初からご自宅に帰られるまで、またご自宅での生活までも援助していきます。
また地域での講習会を開催し、患者様、ご家族様、地域の方々が暮らしやすい環境を整える活動も行っています。 作業療法は、「その人らしい生活」を目指してサポートさせて頂きます。
また地域での講習会を開催し、患者様、ご家族様、地域の方々が暮らしやすい環境を整える活動も行っています。 作業療法は、「その人らしい生活」を目指してサポートさせて頂きます。



言語聴覚療法
言語聴覚療法では、コミュニケーションに問題がある方や摂食嚥下(食べる事、飲み込む事)に問題がある方などに検査、評価、訓練、指導、助言などの支援を行います。コミュニケーションの問題としては、成人領域では失語症(聞く、読む、話す、書くといった能力の障害)、構音障害(口・舌がうまく動かせないことによる発音の障害)、認知・高次脳機能障害、聴覚障害などがあり、小児領域ではことばの発達の遅れ、吃音など多岐に渡ります。コミュニケーションの面から豊かな生活が送れるよう、ことばや聴こえに問題をもつ方とご家族を支援します。また食事の面に関しては少しでもおいしく食事が食べられるよう支援します。





 連絡先を知りたい
連絡先を知りたい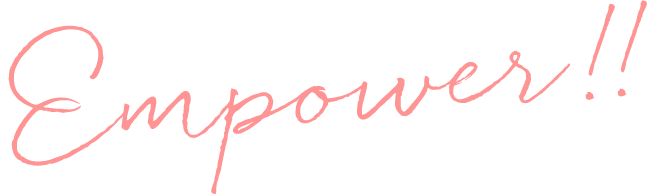 採用サイト
採用サイト